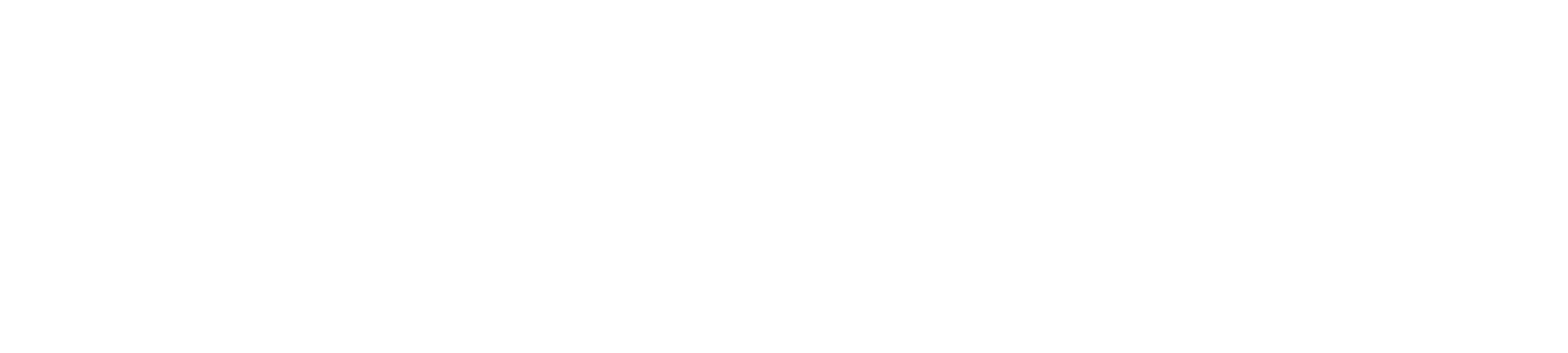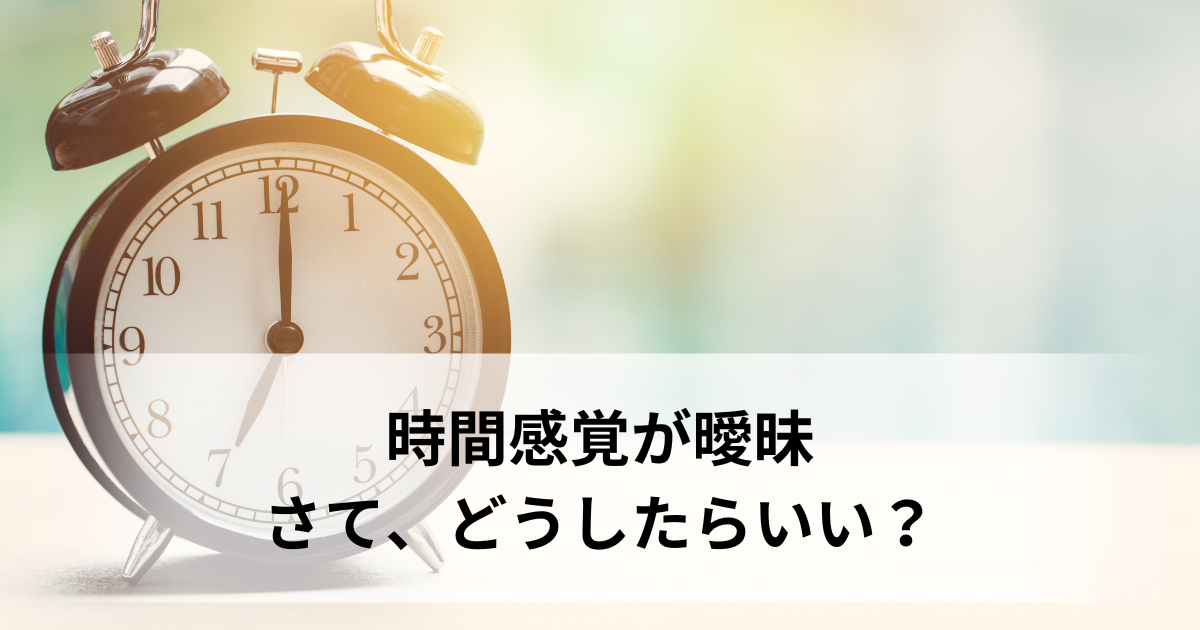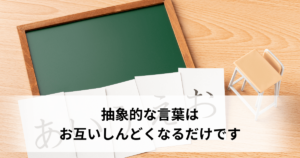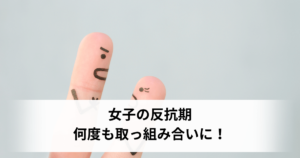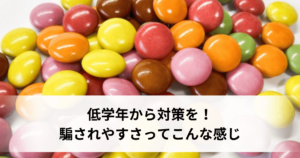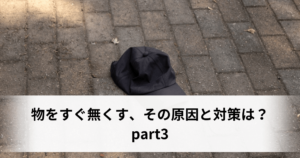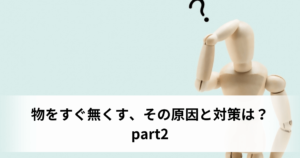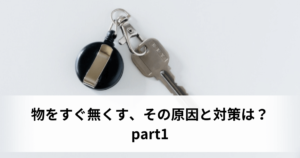娘を育てていて思うのは、
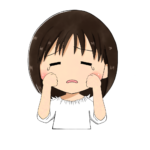
時間感覚が曖昧だなー
という事。
目に見えないので仕方ないですね…抽象的なものにはめっぽう弱いので。
とはいえ、時間の感覚って生きていくうえでなくてはならない大事なものです。すべては時間を基準にして動いていますしね。
というわけで、我が家が娘に時間間隔を養ってもらおうと、色々働きかけてきたことをまとめてみます。
とはいっても、すぐに身につくものではないので、日々、働きかけてみてくださいね。
このブログは、
軽度知的障がいを持つ高校生娘の記録です。
知的障がいと分かったのは3歳8か月の時。
田中ビネー:64 wiskⅤ:70前半です
(療育手帳取得済み)
特別枠を利用し、公立高校に進学。
運動、おしゃべり好きな女子に成長しました。
時間感覚がないってどういうこと?
〇分がどのくらいの長さか、というのが体感的にわからないことです
よく言えばマイペース。
悪く言えば、常に時間に間に合わない。



早くしてよ!
ってお子さんによく言ってませんか?それって、時間の感覚がなくて「急げない」のが原因かもしれないですよね。
娘は「○○分には出かけるからね」と言われたところで、その○○分までがどのくらいの時間の長さなのかわからない。
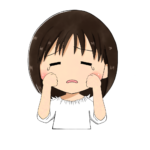
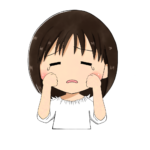
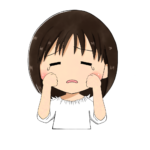
そりゃ…急げませんね。
あ、でも心配しないでください!高校生になった今は、ほぼできるようになってるので、身についていくものですから。
さて、では、我が家の取り組みをご紹介します。
時間感覚を養う取り組み
砂時計を使う
療育の先生に勧められた砂時計。特にこの三角形のタイプの砂時計を勧められました。
こちらは1分、3分、5分という設定。まずは短い時間から慣れていきましょうというお話でした。
時間感覚と言ってもそんなに堅苦しいことはしません。
例えば、お菓子を食べるときに1分タイマーをセットして



あ、もう1分経っちゃったね。1分ってあっという間。これだけしか食べれなかったね。
と声掛けしてみたり。
5分タイマーにして、プリント教材をやってみたり。
日々の生活の中で負担にならない程度に取り入れました。
○○分○○する
とても分かりにくい書き方になってしまいましたが、例えば、



15分だけTV見ていいよ。



ゲームは30分ね。
などという声掛けで、時間を意識させるようにしました。
あとは、



今日のご飯は20分で食べよう!
みたいな感じで、正確に時間を守るというよりは(もちろんそれも大事なんですが)時間に対して意識を向けさせることを重視しました。
娘のように知的障がいがある場合、「その場その場」を生きていて、未来に意識が向くことが難しいことがあったりします。
なので、
人はみんな時間の中で生活していて、生きていっているという事を意識付けできるようにしました。
あと〇〇分、の声掛け
これもよく使いました。
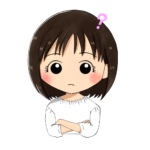
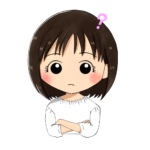
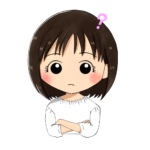
9時まであと何分かな?
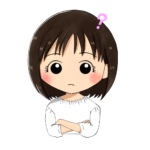
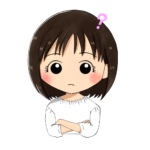
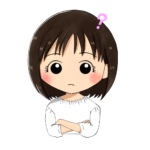
10時30分に出かけたいんだけど、あと何分あるだろう??
そんな感じの問いかけです。「あと何分」がわかることもとても重要で、時間が決まったことに向けて何か準備をしなくてはいけない時には必須事項ですね。
例えば、友達との約束や、電車の時間、仕事の締め時間…
日々の生活の中で、避けて通れないことですよね。これがわかると、だいぶ進歩した気がしました。
身支度には何分かかる?
そして実際、自分の身支度には何分かかるのかを一緒に測ってみました。
例えば朝の支度だと、
着替えるのに〇分、ご飯は〇分、歯磨きは〇分、ランドセルを背負って靴を履いて玄関を出るまで〇分。
1つ1つの動作に〇分かかる、ということを意識させるのと同時に、これを合計して〇〇分、なので、〇時〇分に起きればいいね、と、そういう事も出来ます。
朝の支度については、マグネットシートを作ったと先日記事に書きましたが、それを使いながら順序だてて行いました。


発達障がいのお子さんの場合は、注意が他にそれてしまうことが多い傾向にあるので、朝の支度はルーティン化して順番が変わってしまったりしないように、一連の流れにすることをお勧めします。
時間感覚を身に着けるために
今回は、時間感覚に弱い娘への働きかけについてまとめてみました。
高校生になった今、電車の時刻を調べて、それに合わせて家を出る、という事は難なくできるようになりました。
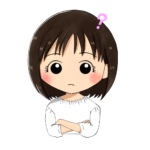
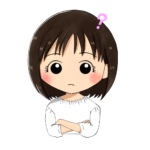
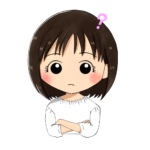
ちょっと早すぎない??
なんてこともありますが(私の感覚より5分くらい早い)、遅刻するよりはいいかなと。
この遅刻するよりいい…というのにもまた問題は起きるのですが…それはまた後日書くとして。
時間の感覚がなくてこれは困ったな‥という親御さんがいらしたら、日々の働きかけと経験でここまでできるようになりますよ、という事をお伝えしておきますね!
数年単位の気の長い働きかけですが、今やっていることは決して無駄にはならないので、日々積み重ねていきましょう!私もまだまだ頑張らなきゃいけないことたくさんです。
それでは!