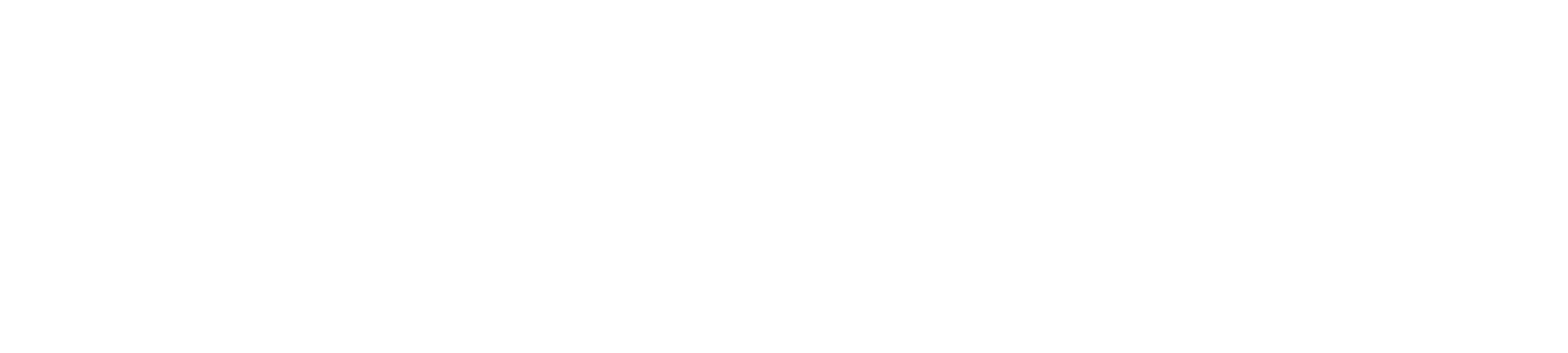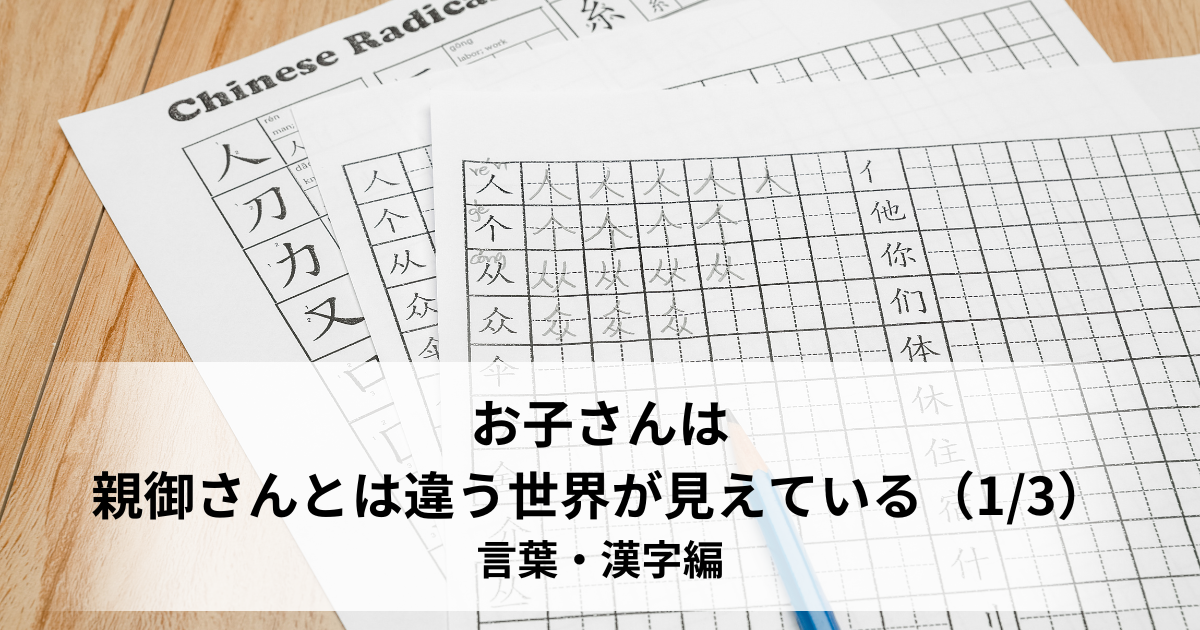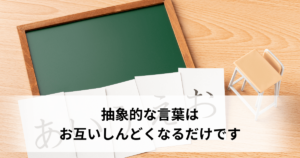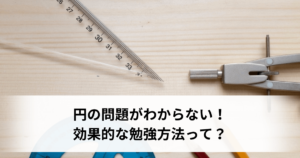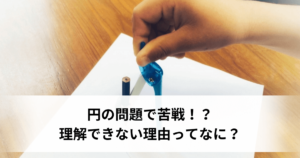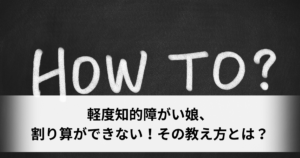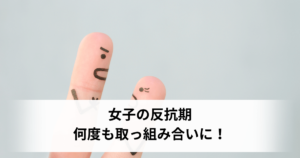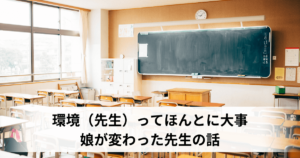「お子さんは親御さんとは違う世界が見えている」
子どもが3歳の時に、発達の先生から言われたのがこの言葉でした。
このブログは、
軽度知的障がいを持つ高校生娘の記録です。
知的障がいと分かったのは3歳8か月の時。
田中ビネー:64 wiskⅤ:70前半です
(療育手帳取得済み)
特別枠を利用し、公立高校に進学。
運動、おしゃべり好きな女子に成長しました。
知的発達がゆっくりな子どもは、
- 言葉や物事の定義があいまいな世界に住んでいるから定型の大人のように、「これは四角」「これは速い」といったくっきり明確な世界ではないかもしれない
- 時間の感覚も理解や把握が難しいものだから、大人とは感じ方が異なるかもしれない
- 空間認識も難しいものだから…(以下同文)
というものでした。

言われた当時は、わかるような、わからないような、お坊さんのありがたいお話を聞いているような感じでした。
要は、よくわからなかったんですね(笑)
その後、子どもが4歳、5歳、小学生、中学生と年齢が上がるにつれて、その言葉の意味がよくわかるようになりました。
まず、言葉については、自分たちが普段、当たり前に使っていることがいかに高度な積み上げをしているのかが子どもを通してよくわかってきたんです。
わかりやすく例を挙げますね。
例えば、「原発」という単語は、「げんぱつ」という音と「原子力で電気をつくるところ、壊れたら大変なところ」という意味、「原発」という漢字(文字)の3つがセットになっていますよね。
けれど、小学校1~6年生の頃の娘は、「げんぱつ」ではなく、「でんぱつ」(実際には、「げ」と「で」の中間のあいまいな発音)と認識したり、原発の意味が分からなかったり、漢字もわからなかったりで、とにかくあいまいでした。
これは「原発」という言葉だけの話ではなくて、日常で使う言葉の中にも、音が分からない、意味が分からない、音はわかるけれど意味と漢字が分からないなど、いろいろな組み合わせでわからないことがたくさんあったんですね。



音にしても意味にしても、イメージにしても、すべてが曖昧な世界観だったんです。
そうなると、「漢字を覚える」という事ひとつとっても、読みを日常で使ったことがない、聞いたことがない(認識したことがない)漢字を形だけ覚えるとても難しい作業になるんですね。
私たちは通常、自然に色々な言葉の組み合わせとして熟語を覚えたり、漢字の意味を考えて記憶と結びつけたりしていますが、それができない…なので意味のない記号を覚えたようなものですぐに忘れてしまう。応用もできない。
これに気づいたときに、漢字の定着が悪い理由、漢字だけではなくて、記憶の定着が悪い理由がよくわかるようになりました。
当然、親としては、子どもがそんな世界にいるとはまったく想像できないところからスタートなので、小学校高学年になるまでは、無駄に怒ったり、無駄に子どもを責めたり、落胆したり、その繰り返しでした。
娘の言葉へのあいまいな世界が見えてきて初めて、発達の先生の言葉の意味がようやく「そういうことかも!」とつながりました。
(2/3に続く)