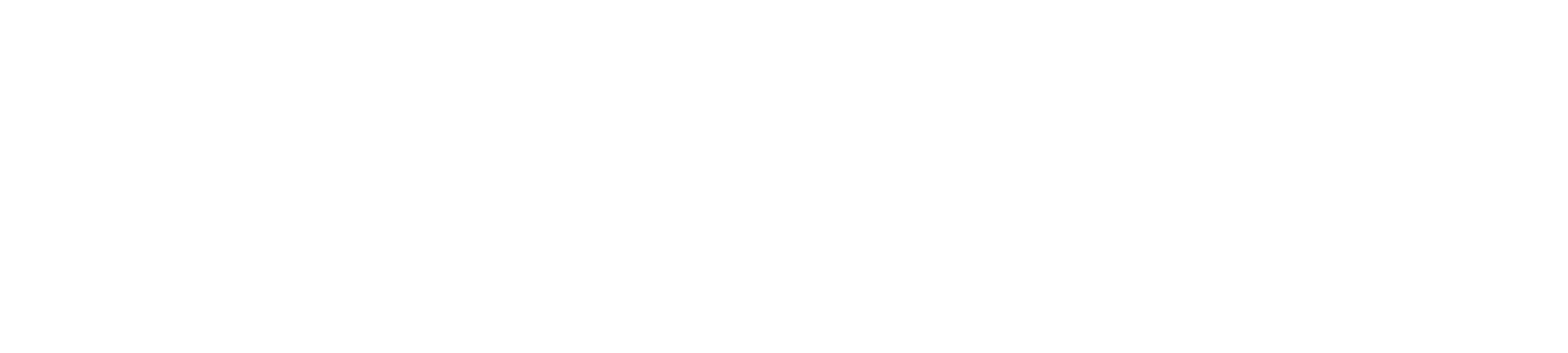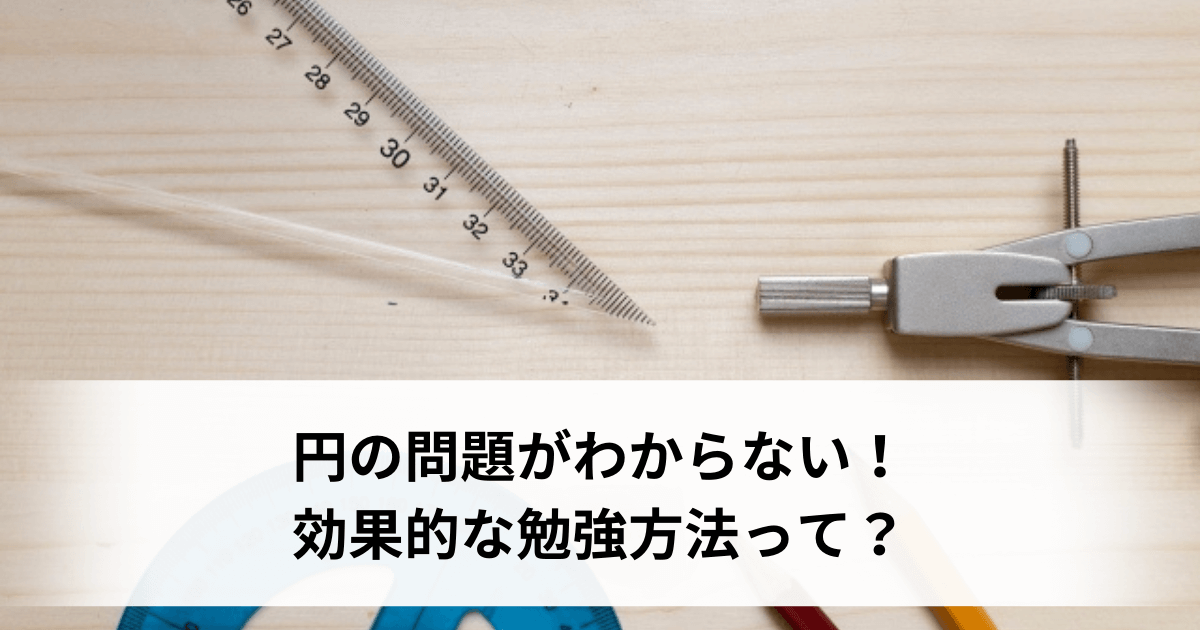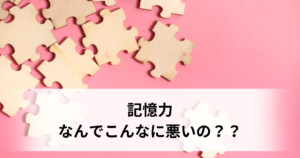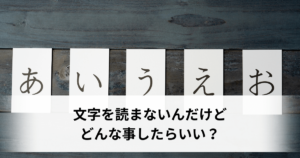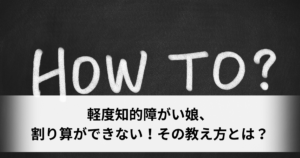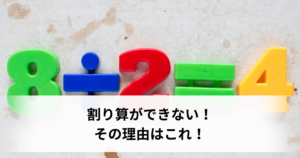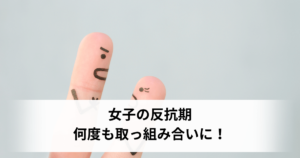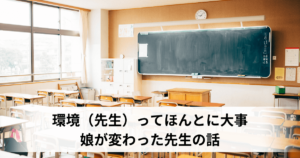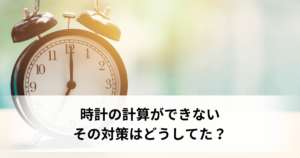前記事では、
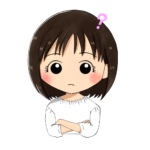
円の問題で苦戦する理由って何だろう?
という内容をまとめてみました。
今回は、前回の続きで、
「うちの子、円の単元がなかなか理解できないみたい…」
「何が理解できていないんだろう?」
「どう教えたらいいんだろう?」
と悩む親御さんに、娘にどうアプローチしてきたのか、具体的にまとめてみますね。
前の記事からの続きになりますので、こちらから読んでもらえるとわかりやすいと思います。
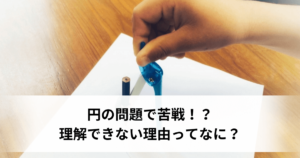
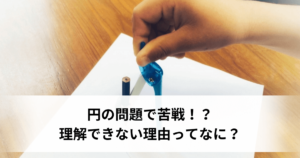
このブログは、
軽度知的障がいを持つ高校生娘の記録です。
知的障がいと分かったのは3歳8か月の時。
田中ビネー:64 wiskⅤ:70前半です
(療育手帳取得済み)
特別枠を利用し、公立高校に進学。
運動、おしゃべり好きな女子に成長しました。
円について、どういう方法で勉強した?
①語句の暗記
まずは「半径」「直径」「中心」「円周」といった基本的な言葉の意味の理解を進めました。
表現は色々あるので、お子さんが理解しやすいものを探してみるといいと思います。
・円周:円の周り、円を作っている〇の部分、外側のカーブ
・中心:円のちょうど真ん中、円周のどこからも同じ距離のところ
・半径:中心から円周まで、円周から中心をとおってまっすぐ線を引いた真ん中まで
・直径:円周から中心をとおってまっすぐ線を引いたもの



説明ってとても難しいです。お子さんによっても理解できる言葉は違うでしょうから、あの手この手で探してみてください。
②とにかく具体物
実際にコンパスを使って円を描いたり、厚紙に円を書いて切り抜いたりして、感覚的に理解できるようにしました。
・「半径」「直径」「中心」「円周」それぞれの部分を強調した図を描く。
・円周などは、糸を使ってぐるっと巻いてこれが「円周」と表現する。



とにかく、具体物、手を動かす、目で見てみる、これを大事にしました。
そんな中で、円周って思ったより長いんだねなんてことも分かって来たりします。
③スモールステップで
一気にたくさんのことを教えようとせず、少しずつステップを踏んで学習を進めました。
どうしても私たちの感覚だと一気に覚えるもの、という感じがしますが、似たようなものを一気に覚えようとするとどうしても混乱します。
時間はかかりますが、1つ1つのことをしっかり定着させたうえで進めていくことをお勧めします。
④繰り返し練習
あとは、何度も繰り返しの練習ですね。
今ではネットでもプリント教材がありますし、問題集も出ていますから、そこは惜しまず反復練習をしましょう。
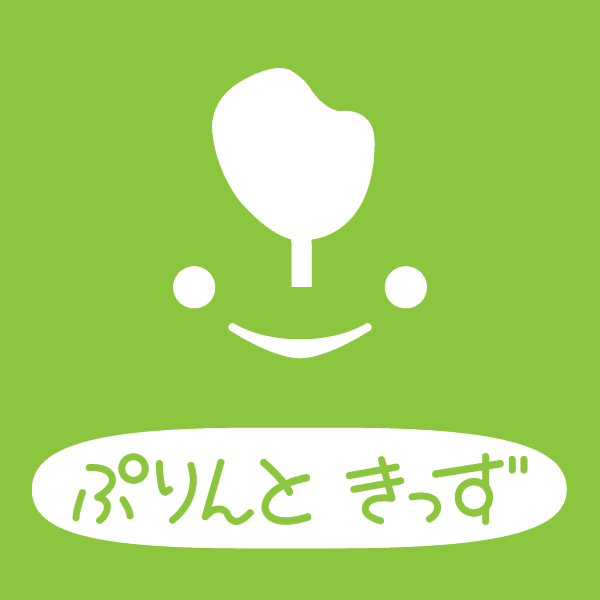
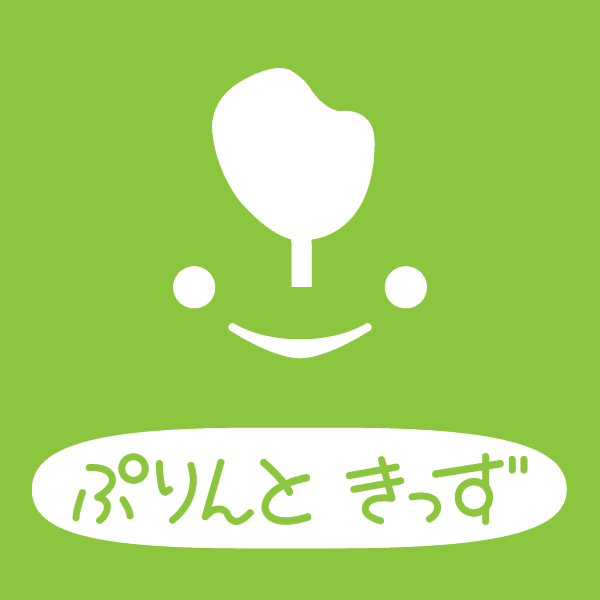



円と球の単元のみリンク貼りましたが、ふたつのサイトはどちらもかなりプリント教材が充実しているので、おすすめです!
まとめ
円の問題を理解するには、まず基本的な言葉の意味を理解することが重要です。
その上で、具体物や視覚的な教材を活用しながら、スモールステップで繰り返し練習することが効果的です。
イメージ力が弱いという特性がある場合、図形の理解ってとっても難しいです。
こんな勉強、社会に出たら使わないよ。と思う事もあるかもしません。
でも、やっぱりできるところまでの知識は得てほしい。
円のことを直接的に将来何かに役立てる、という事はほぼないでしょうが、一般的な知識として持っていてほしい、そんな思いで私も日々取り組んでます。