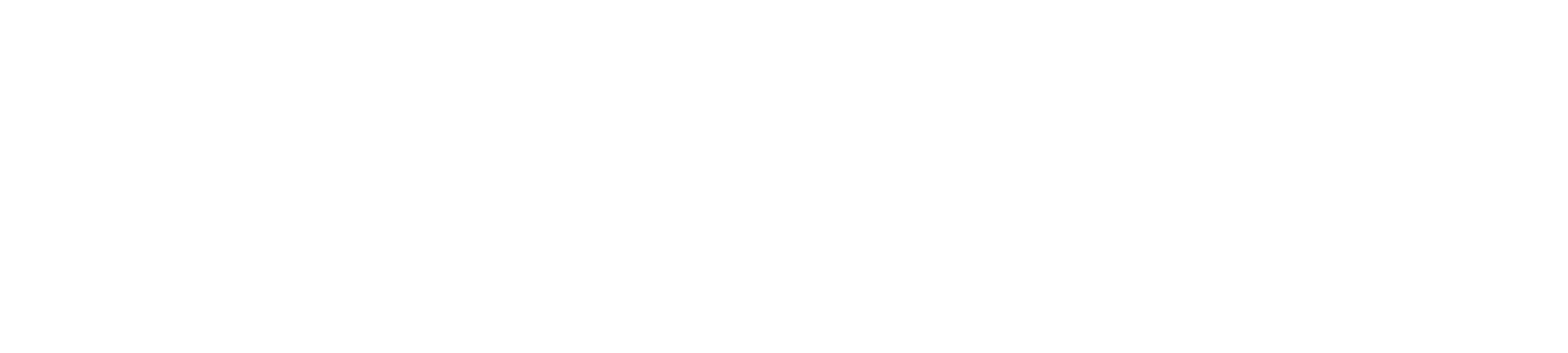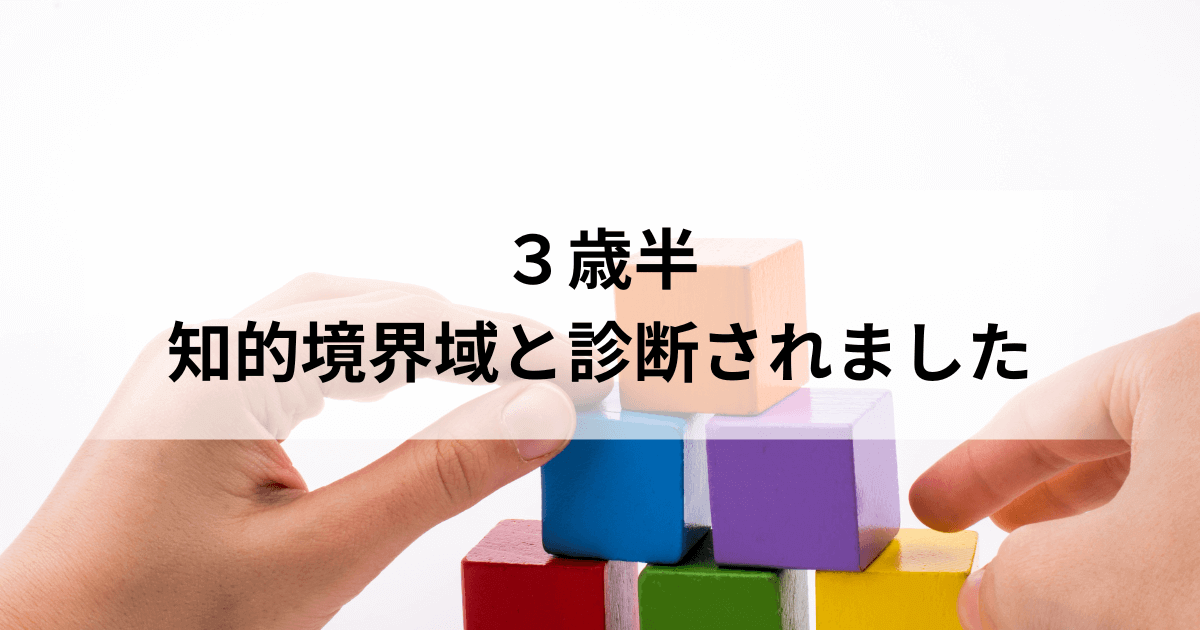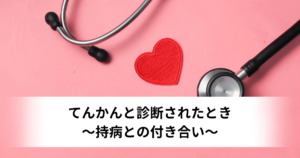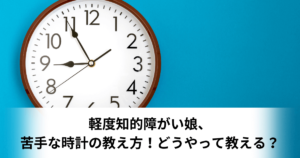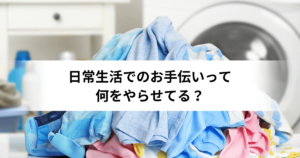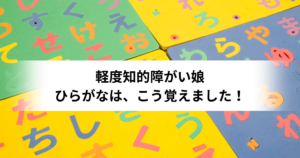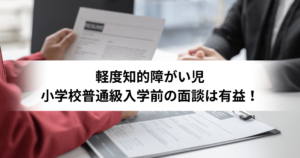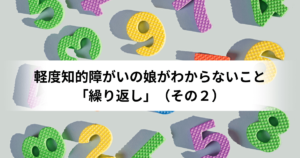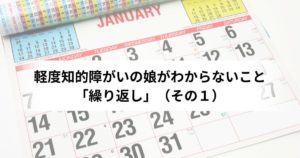娘は3歳8か月の時に知的境界域という診断が出ました。当時の私は発達のことにほとんど知識がなく、
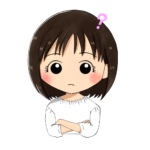
それってどういうこと?
お子さんに関して気になるところはあると思いつつも、個人差、個性、まあそのうち成長するだろう、そんなふうに考えるのが一般的だと思います。
- 知的障がいってどうやったら正式にわかるの?
- 子どもが知的障がいと分かったらどうするの?
- どんなことで知的障がいかもって気づいたの?
そんなことを含め、まとめていきますね。
このブログは、
軽度知的障がいを持つ高校生娘の記録です。
知的障がいと分かったのは3歳8か月の時。
田中ビネー:64 wiskⅤ:70前半です
(療育手帳取得済み)
特別枠を利用し、公立高校に進学。
運動、おしゃべり好きな女子に成長しました。
知的境界域の診断
3歳8カ月で受けた発達相談で、「知的境界域」と言われた娘。
「半年遅れ」との診断でした。
この「半年遅れ」という言葉、聞いた時は正直言って、大したことないじゃん、と思ってました。半年だけだと。
当時の私の感覚としては、半年の遅れだけで、知的にボーダーって言われてしまうんだー、厳しいんだねー、くらい。
けれど、約3歳半の年齢の「半年」というのは相当大きくて、よくよく考えてみたら3年半で半年分も差がついてしまっているという事なんですね。
成長って表現が難しいですが、知識の上に知識が乗っていく感じなので、いったん遅れると差は広まっていくもの。
それを私が実感するのはまだ後のことですが、なにかしら働きかけをしていかないといけないものなんだと、素人なりに突き付けられた診断でした。
発達相談を受けることになった言葉の遅れ
前後しますが、発達相談をなぜ受けたか。
それは本当に偶然で、持病の検査入院をしたことからでした。
いくつかの検査をしなくてはならず、1週間ほど入院。ずーっと検査をしているわけではないので、検査がないときは基本自由時間です。
病院のHPを見ていたら、「お子様の発達で気になることがあれば相談も受けています」と。そこにあったのが
言葉が遅い
という記載でした。
当時、言葉の遅さはそこまで感じていませんでしたが、
- 話す文章が短い
- 同級生に比べて、短文・単語が多い
ということが少し気になっていました。4歳前になると女の子は本当によくしゃべるようになって、これでね、あれでね、と文章が続いていくお友達も多かったのです。
それに比べるとだいぶ淡泊な話し方をするなーという程度だったのですが、どっちにしろ自由時間もたくさんあるし、と気軽に受けた相談でした。
もしこの時の検査がなかったら、「長く話すのが面倒な性格なんじゃない?」とか「人それぞれだしね」とそれでスルーしていた程度の認識でした。
三歳半ごろ:知的境界域で困っていたこと
この頃、困っていた(気になっていた)こととしては先ほど書いた
- 話し言葉の文章が短い
- あれ、それ、など指示語が多い
- 話し方が唐突
くらいで、言葉についてが多かった気がします。
今から思えば、ボキャブラリーが少なかったのと、単語の覚えが悪かったので(ワーキングメモリの少なさ)文章が短かったり、指示語が多かったりしていたんですね。
なので、いつも一緒にいる親なら理解できることも、お友達だと「何の話だろう?」と一瞬戸惑ってしまうこともあったように思います。当時はまだ親と一緒にいることが多いので、私が何の気なしに「○○のことでねー」とフォローを入れていました。
やり取りはできるものの、大人がいてよりスムーズになるという状態といえばいいのかな?
ただ、体を動かすことに関しては特に問題はなく、
- 着替えやボタンなどの身支度
- トイレや入浴
- かけっこや遊具での遊び
そういったことに関しては、お友達と同じようにこなしてましたので、より分かりづらかったのだと思います。
知的境界域と診断されたその後
発達相談で知的境界域と診断された娘。
私は上でも書いた通りその重大さをあまりわかっていなかったのですが、ちょうど3歳8か月という年齢だったこともあり、そこから
- 幼稚園探し
- 療育機関探し
が始まることになりました。(プラスして持病のかかりつけも探すことになりましたが)
娘との生活で、特段不自由を感じていたわけではなかったので、この時点ですぐに療育が必要とはその時全く頭にありませんでした。
でも、この療育がなかったら、娘が何ができて何ができないか、それについてどうやって接して、どうやって苦手を埋めできることを伸ばしていけばいいのかがわからないままという恐ろしいことになっていたと思います。
幼稚園探し、療育機関探しについては別記事で詳しく書きますが、発達に理解のある先生たちとの出会いは、この先どうなってしまうんだろうという不安の中での本当に大きな心の支えになりましたし、娘が今学校生活を楽しめているのも娘の適性を見極め、うまく導いてくださったからです。
これからのことに不安が大きいと思いますが、まずはひとつひとつその不安をつぶしていきながら、やれることをやっていくことが大事だと思います。