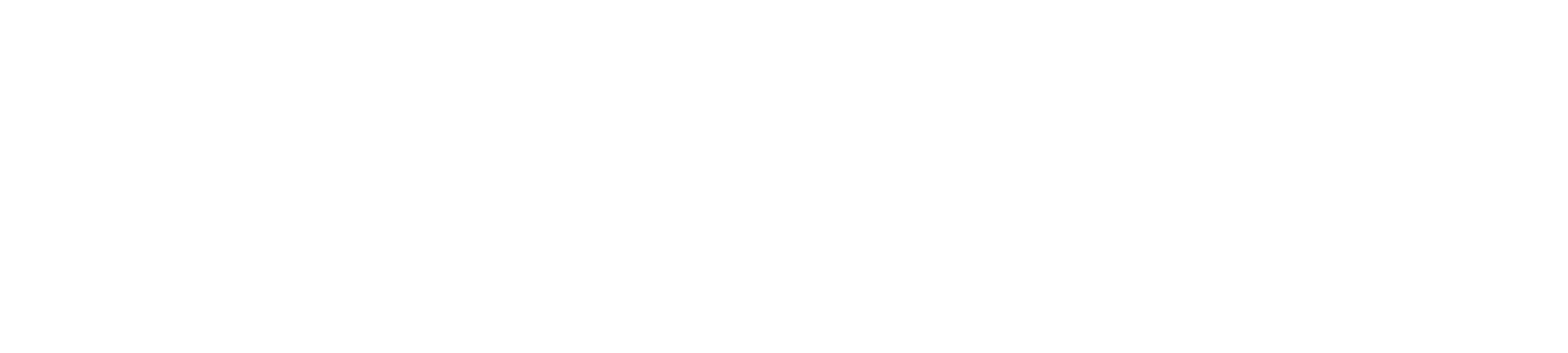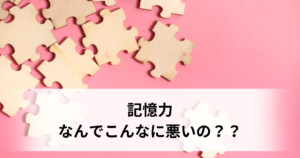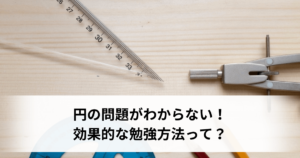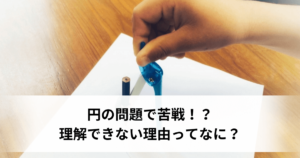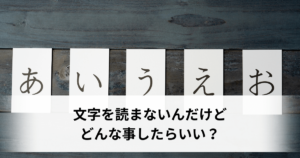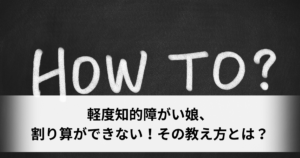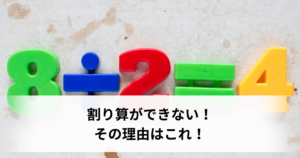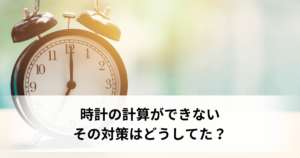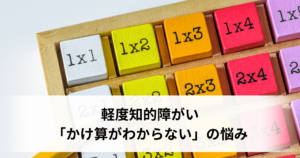発達障がいや知的障がいの子どもを持つ親御さんの中に、
「勉強をさせなくてはいけないと思っているが、どんな勉強をすればいいか」
「どんな教材を使えばいいか悩んでいる」
という方も多いのではないでしょうか。
今回は、娘の体験を踏まえて、知的障がい児の勉強について、
- 具体的にどんなことをしていたのか
- どんな教材を使っていたのか
など紹介したいと思います。
具体的に何を勉強していた?
分野別に書いていきますね。
漢字
漢字は読めて損のないものです。療育の先生から
6年生までの漢字が読めれば新聞の大見出しが読めます
と言われたこともあり、小学生の漢字をしっかり身に着けることを目標としてきました。たまたま、中学時代に学校で漢字検定を受験できる機会があり、継続して受験。
小6で3年生レベル(8級)
中1で4年生レベル(7級)
中3で5年生&6年生レベル(6級&5級)
と、段階的に挑戦して合格。
今は次の4級を目指して頑張っています。漢字検定は、本人のモチベーションアップにもつながっていて、「合格」という文字が

私は漢字が得意なんだ!
という自信にもなっています。ゆっくりの進度ですが少しずつでも読める漢字や語句を覚えていってくれるといいなと思ってます。
漢字は生活に密着しているし、今後いろいろな資料や書類を読むのにも必要なので、できる限り継続して挑戦してもらいたいですね。
計算
計算はとっても苦手な娘ですが、とにかく
+-×÷の何を使って計算するか
という事をしっかり把握できるように練習しています。
娘はこれが苦手。電卓があるから大丈夫、と言われたこともありますが、
いやいや…そもそも何算で計算するかわからなければ計算できません。
- 買ったらいくらになるか
- 分けたらいくつになるか
- お釣りはいくらになるか
- 2人分のレシピを4人分にするにはどうしたらいいか…
こういった生活で使う算数はできるように日々考えさせて練習しています。
+-×÷ができる前段階ですね。
すんなりできればいいのですが、まだまだ迷ってしまう事があり、常に練習が必要だと感じています。
社会の地理
せめて日本地理、大きな国は世界地理もわかるように、と思っています。その辺は常識の範囲なので、身に着けてもらいたいな…ただ、なかなか難しいようです。
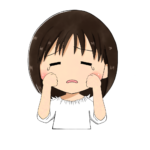
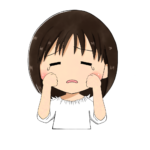
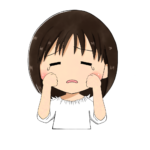
県名がわかっても、○○地方、というのがなかなか覚えられなかったり…
世界地理は、ニュースでよく出てくる国名、その場所がわかるようにしていますが、それもなかなか…(涙)
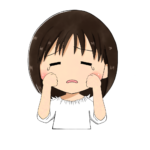
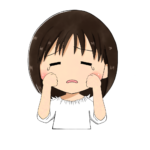
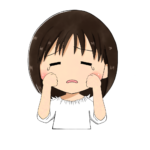
国名と大陸名が混じってしまったり、地図の中心が動くとわからなくなったりしてしまいます。
身近にある理科的なこと
以前に季節感がなくて困るという記事を書きましたが、意識的に季節ものを学ぶようにしています。例えば、春は桜の花、夏はスイカやメロン、秋は紅葉、冬は雪など
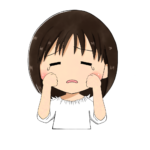
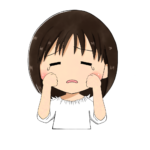
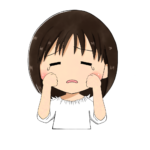
放っておくと気に留めずに過ごしてしまうんですよね。
まとめ
分野別に書いてきましたが、こんなふうに基礎的なことをくり返してます。
基本にある私の思いは



一般的な常識は身に着けてほしい
という事。
娘自身の自立もそうですが、人と話すときに「??」となっても困りますしね。日々、少しずつでも積み上げていければと思ってます。
今回は娘と私が取り組んできたこと、取り組んでいることについて具体的にまとめてみました。
参考にしていただければ嬉しいです。