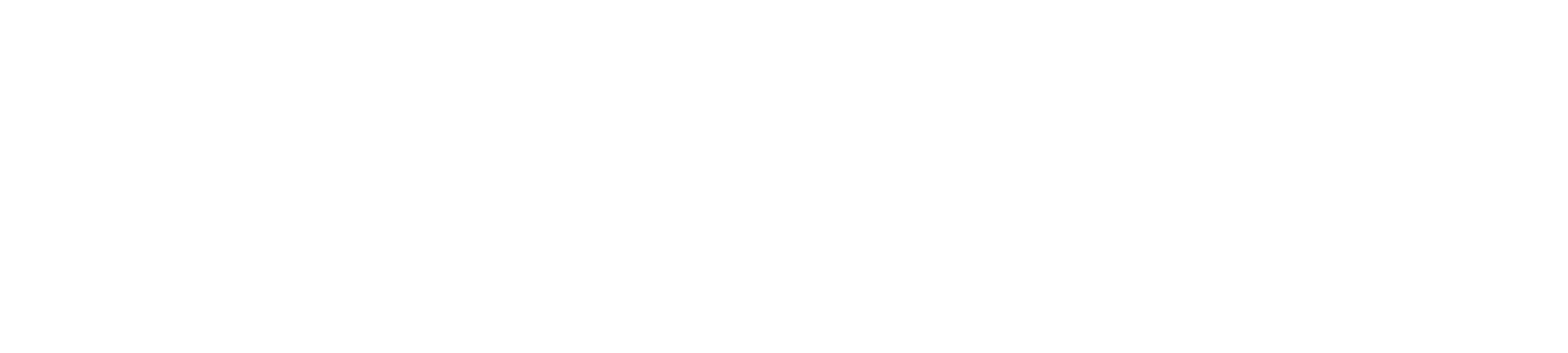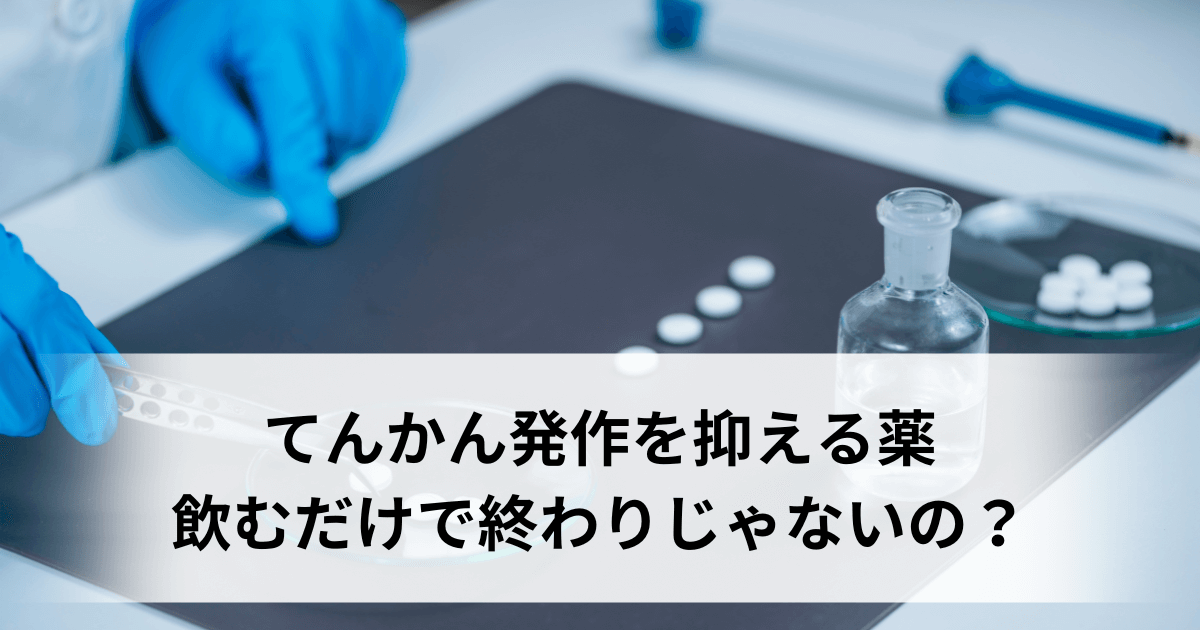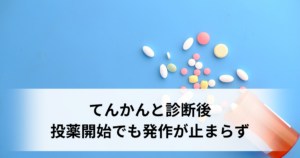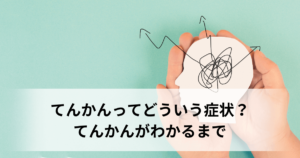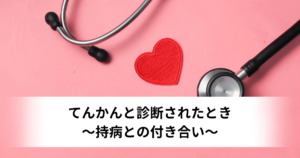前記事に書いたように、静岡てんかんセンターでてんかんの検査をして、いよいよ本格的に
薬の調節が始まりました。
「てんかんと診断されたら?」
「薬って飲むだけじゃダメ?」
「てんかん薬の調節って何?」
親御さんの、そんな疑問に答えます。

デパケンでは止まらなかった発作
最初は、地元の病院でデパケンを処方されました。てんかんと診断されて、真っ先に処方された薬。
てんかんと言えばまずデパケンと言われてるくらいポピュラーな薬とのことで飲み始めましたが、前記事にも書いたように、発作は止まらず。
この頃は量の調節があることもまだ知らず、とにかく
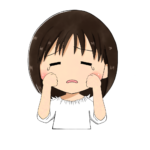
飲んだ→発作止まらない!
と、焦っていた段階でした。
てんかん薬は飲んで終わりではない
静岡のてんかんセンターで初めて、てんかん薬は、飲むだけで終わりではないことを知りました。それもママさんたちから。



どの薬がどの量で発作に効くかを調節していくという治療が必要なのよ、と。
薬の調節はとても難しくて、少なすぎても多すぎてもダメらしく、その調節に苦労していると。全く青天の霹靂。飲めば治るんじゃないんだと知った検査入院でした。
薬の量を増やしすぎても副作用。少なすぎても発作が止まらない…。
なのでみなさん、長期入院して薬の調節をしていたのです。



血中濃度を測りつつ、脳波検査をしつつ、薬の増減をしていくんですね。
これは本当に長期的な戦いになるんだと、覚悟しました。
薬の調節とは?
てんかん薬の調節は、ざっくりいうとこんな感じです。
- 1剤目の薬を処方します。
- 1剤目の薬の量を、少しずつ増やしていきます。
- 1剤目の薬の量を血中濃度で可能な最大量まで増やしても発作が止まらない場合は、別の薬を追加します。
- 2剤目の薬の量も、1剤目と同じように調節していきます。
- 2剤目の薬も最大量まで増やしても、発作が止まらない場合は、別の薬を追加します。
この繰り返しをしながら、発作を抑える薬と量を見つけていきます。効いてないなと思われる薬があれば、減薬も同時にしていきます。



前にも書きましたが、減薬のほうが怖いので、本当に少しずつ減らしていきます。
1剤目はデパケン
娘の場合、1剤目は地元の総合病院で処方されたデパケンでした。
デパケンの血中濃度をマックスまで増やしましたが、発作は止まりませんでした。
もしかしたら脳波は少しきれいになっていたかもしれません。
2剤目はエクセグラン
次に、2剤目としてエクセグランを追加しました。
若干さらに脳波はきれいになったかもしれない、と言われましたが、発作の数は変わりませんでした。
3剤目はラミクタール
当時、娘の発作は、1日30回ほど。
転倒したり意識消失する発作ではなかったですが、発作が起きると脳が疲れるのか少しの間寝てしまっていたので、見ていてほんとしんどかったです。
詳しくはまた書きますが、てんかんセンターの担当先生とは別に、地元で薬の調節をしてくださる主治医の先生が必要で、8月の頭にその先生とつながり、新しい病院で診療が始まりました。
そこからエクセグランをマックスまで増やし、そのあと3剤目としてラミクタールを処方。
てんかん薬は処方してから効きだすまで1週間から10日とのことで、増量して待機。変化がなかったら先生に報告→増量…の繰り返しです。
そして、忘れもしない12月頭。
あんなに毎日起きていた発作が、ピタッとおさまりました。
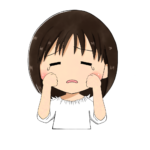
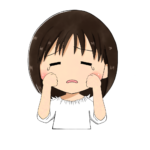
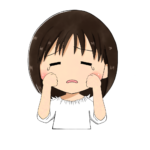
これが最後の発作だったらどんなにかありがたいのに…
と思いながら、毎日娘と過ごし、希望と落胆を繰り返してきましたが、本当に先生の薬のチョイスと調節に感謝した瞬間でした。



てんかん薬の種類はたくさんあるので、その中からどの薬を選ぶのかにも先生の腕がかかっています。
あれ?今日発作ない…と思う日が日々増えていき…かれこれもう12年です。
てんかん薬の調節には時間がかかります
今回、てんかん薬の調節について書いてきましたが、初めて様子がおかしいのに気づいてから、1年以上が経っていました。
薬の調節には本当に時間がかかるものです。その間娘がどうなってしまうんだろう、不安や焦りでいっぱいでした。
合う薬が見つかったことに本当に感謝しなくてはいけないよ、と日々娘には言い聞かせながら過ごしています。
まとめ
今回は、てんかん発作を抑える薬、飲むだけじゃなくて調節が必要なんだという事について、我が家の経験をまとめてみました。
飲んだらすぐ治る病気ではありません。(もちろんその場合もあると思います!)
なかなか発作が収まらずに、焦りと不安だらけになる日常でしんどいこともたくさんあります。
でも、こうやって発作が止まった我が家のような例もあるという事が、てんかんを持つお子さんがいらっしゃる親御さんの希望になれるよう、今回記事をUPします。
薬の開発は現在進行形でしょうから、一刻も早く合う薬が見つかることを祈ってます。